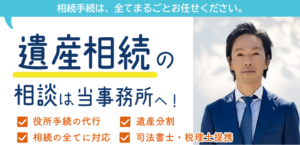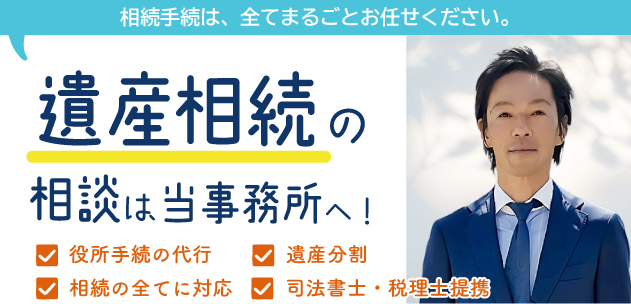
相続によって田舎にある山林や農地、空き家などの所有者となったが、遠く離れているため、自分で使用することもないし、借り手も買い手も見つからないため手放すこともできず、管理と固定資産税の支払いだけを引き受けることとなってしまっているという事案が多く聞かれます。
特定の相続財産だけを相続放棄するということができないため、活用が困難な不動産も含めて相続したものの、遠く離れた実家周辺の不動産には管理が行き届かないという相続人側の課題がある一方、当該不動産の所在する地域では、空き家による景観や治安の悪化の問題、耕作放棄による農地の荒廃の問題が社会問題化しています。
このような社会問題を解消するため、国においては、「空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)」の制定等により管理の行き届かない空き家の解消を推進するとともに、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)」を制定し、管理や活用の困難な相続した土地の国による引き取り制度(相続土地国庫帰属制度)が令和5年4月27日から開始されました。
→e-Gov法令検索(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律)
ここでは、いまや相続における大きな問題である「活用が困難な手放したい不要な土地」を国が引き取る「相続土地国庫帰属制度」の概要を紹介するとともに、相続土地国庫帰属制度の対象とならない空き家への対応方法について解説したいと思います。
- 1. 相続土地国庫帰属制度について
- 1.1. 国による引き取りの対象とならない土地
- 1.1.1. 建物の存する土地
- 1.1.2. 担保権又は使用・収益権が設定されている土地
- 1.1.3. 通路その他の他人による使用が予定される土地が含まれる土地
- 1.1.4. 汚染されている土地
- 1.1.5. 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
- 1.1.6. 崖があり、管理に過分の費用・労力を要する土地
- 1.1.7. 管理を阻害する工作物などがある土地
- 1.1.8. 取り除く必要のある有体物が地下にある土地
- 1.1.9. 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
- 1.1.10. その他、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地
- 1.2. 申請人の要件について
- 1.3. 申請期限について
- 1.4. 申請先について
- 1.5. 審査期間について
- 1.6. 費用について
- 2. 相続した空き家の処分について
- 3. 無料相談のご予約は こちら
- 4. 対応地域
相続土地国庫帰属制度について
相続土地国庫帰属制度は、上述のとおり、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)」に基づき、令和5年4月27日から開始された新しい制度ですが、既に法務省には3,854件の申請があり、1,699件が国に帰属しています。(ともに令和7年5月31日現在の法務省速報値)
申請のあった土地の地目は、田・畑:1,490件、宅地:1,336件、山林:600件、その他:428件となっており、宅地であっても活用ができない又は不要とされる土地が多いことが伺えます。なお、制度の詳しい利用状況については、法務省HP(相続土地国庫帰属制度の統計)をご覧ください。
それでは、相続土地国庫帰属制度について、その内容を紹介していきたいと思います。
国による引き取りの対象とならない土地
まず、どのような不動産が対象となるかですが、残念ながら、建物はその対象とならず、また、建物のある土地についても対象外とされています。
これは、国においても、引き取った以上は管理責任を果たすべく、日々の管理を費用をかけて行っていく必要があることから、管理不全となる不動産の減少という政策目的の実現と国庫費用とを天秤にかける必要があったことからの帰結であるといえます。
また、これらに加え、国による管理責任の遂行上問題を生じる可能性のある土地も対象外とされており、以下に対象外となる土地を挙げておきます。
建物の存する土地
建物がある土地については、申請段階で直ちに却下されることとなります。
なお、建物はすでに取り壊されているが、建物登記だけが残っているという土地については、後々建物滅失登記が必要になりますが、申請することが可能です。
担保権又は使用・収益権が設定されている土地
抵当権などの担保権、地上権、地役権、賃借権などの使用収益権が設定されている土地も、申請段階で直ちに却下されることとなります。
なお、一般的にはこれら担保物権や用益物権は、登記してない場合には、所有権を譲り受けた者(相続土地国庫帰属制度については国)に対抗することはできないため、土地の登記簿を確認すればよいという風に考える人が多いかと思いますが、農地に設定された使用権など登記なくして第三者対抗力を備える権利も存在する点には注意が必要です。
また、電力会社や通信会社が電柱や電線を引きために設定した地役権や区分地上権などがある場合は、法務局・地方法務局にて相談対象となるようです。これらについては、土地への制限が限定的であり、使用収益権の設定されてないものと同視し得る場合があるということからの取扱いでしょう。
通路その他の他人による使用が予定される土地が含まれる土地
土地内に通路がある土地や多数の人が利用する水を貯めている池その他水路などを含む土地なども、申請段階で直ちに却下されることとなります。
このような土地にはその使用に係る関係者が多く存在し、国ではその調整まで負担できないからです。
汚染されている土地
土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地についても、申請段階で直ちに却下されることとなります。
汚染の基準値については、土壌汚染対策法施行規則第31条第1項及び第2項の基準を超える特定有害物質により汚染されている土地とされています。
境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
隣接土地の所有者と境界の争いがあったり、他に所有権を主張する者があったりする場合も、申請段階で直ちに却下されることとなります。
なお、土地の境界が明らかである土地であることが要件とされる点については、相続土地国庫帰属制度を申請しようとする相続人にとっては気になるところです。土地を現地で測量し、図面に座標点を落として必要書類を作成し境界確認書まで提出する必要があるとすれば、これだけで数十万円の費用がかかってしまうこととなりますが、法務省によると「測量や境界確認書の提出まで求めるものではありません。」とのことですので、申請のハードルはかなり下がることとなります。
ただし、現地に境界を示す目印があり又は設置し、それを表示した図面を提出することは必要となるため、公図や現地写真を申請の際には添付します。
崖があり、管理に過分の費用・労力を要する土地
勾配30度以上、且つ、高さ5メートル以上の崖があり、通常の管理に当たり過分な費用又は労力を要する土地は、審査の段階でこれに該当すると判断された場合に不承認となります。
過分な費用又は労力の例としては、隣地への土砂の流出を防止するために擁壁工事などが必要となるなどが挙げられます。
管理を阻害する工作物などがある土地
自動車が放置された土地であったり、管理に支障が出るような工作物がある土地である場合、審査の段階でこれに該当すると判断された場合に不承認となります。
法務省による説明では、樹木であっても定期的な伐採をしなければ周辺に悪影響を与えるような場合も含むとされており、多くの場合に本項に該当しそうにも思われますが、公道や家屋に隣接する土地から生える樹木を想像していただければよいでしょう。これらは、伸びてくると伐採や枝打ちが必要となるため、定期的なこのような管理は国では致しかねるということです。
山の中にある土地に樹木があったとしても、これには該当しないと思われます。
取り除く必要のある有体物が地下にある土地
除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地は、審査の段階でこれに該当すると判断された場合に不承認となります。
有体物の例としては、産業廃棄物や瓦、管など多くのものが該当する可能性がありますが、除去しなくても土地の通常の管理が行える場合、例えば、広大な土地の片隅に小規模な配管がある場合などは国への帰属の承認対象となります。
隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
少し抽象的な表現ですが、例えば、民法上袋地にはその周囲の土地を通って公道に出る権利である「囲繞地通行権」が認められていますが、この権利の行使が事実上阻害されている場合などが該当します。
このような土地の管理を行うには、囲繞地通行権の行使を周囲の土地の地権者等に主張する必要が出てきますが、国においてはそこまでの労力がかかる土地は引き取れないということです。
その他、不法占拠者がいるような土地についても同様、審査の段階でこれに該当すると判断された場合に不承認となります。
その他、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地
以上に紹介した以外にも、管理に過分の費用・労力がかかるため、相続土地国庫帰属制度の対象外として法務省が示す例を以下に紹介します。
①災害の危険により、土地や土地周辺の人、財産に被害を生じさせるおそれを防止するため、措置が必要な土地
②土地に生息する動物により、土地や土地周辺の人、農産物、樹木に被害を生じさせる土地
③適切な造林・間伐・保育が実施されておらず、国による整備が必要な森林
④国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地
⑤国庫に帰属したことに伴い、法令の規定に基づき承認申請者の金銭債務を国が承継する土地
申請人の要件について
相続土地国庫帰属制度の利用を申請できる土地については、上記で紹介した土地に該当しないものということになりますが、制度を利用するには、その土地を相続や遺贈によって取得した所有者が申請を行う必要があります。
まず、押さえておく必要があるのは、所有権の取得原因が相続又は遺贈であるということです。よって、売買契約によって土地を取得した場合には相続土地国庫帰属制度を利用することはできません。
また、相続や遺贈によって複数人が所有することとなった共有名義の土地については、共有者全員で申請する必要がありますが、相続又は遺贈によって土地の共有持ち分を取得した相続人がある場合には、その他の共有者とともに申請することによって制度利用が可能となります。なお、相続人でない受遺者、生前贈与の受遺者などは申請することができません。
申請の代理については、未成年後見人や成年被後見人など法定代理に限られ、任意代理人による申請を行うことはできませんが、行政書士、弁護士、司法書士による申請書類の作成代行は認められています。
申請期限について
相続土地国庫帰属制度の開始(令和5年4月27日)より前に相続等によって取得した土地についても、本制度の対象となります。
例えば、数十年前に相続した土地についても対象となります。
申請先について
申請は、相続土地国庫帰属の承認申請をする土地が所在する都道府県の法務局又は地方法務局(本局)の不動産登記部門です。支局や出張所では申請を受け付けてもらえません。
審査期間について
審査は、申請から帰属の決定(却下、不承認の判断を含む。)までに8か月程度かかります。
費用について
相続土地国庫帰属の申請人は、国に対して、①審査手数料と帰属の承認を受けた場合に必要となる②負担金を納付する必要があります。
審査手数料
審査手数料の金額は、土地一筆当たり14,000円です。申請時に、申請書に審査手数料額に相当する額の収入印紙を貼って納付します。
手数料の納付後は、申請を取り下げた場合や、審査の結果却下・不承認となった場合でも、手数料は返還されないため注意が必要です。
負担金
負担金については、承認された土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定した額の負担金を納付しなければなりません(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律第10条1項)。
各地目ごとの負担金は、以下のように定められています。
【宅地】
面積にかかわらず、20万円。ただし、都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の宅地については、面積に応じ別途算定されます。
【田畑】
面積にかかわらず、20万円。ただし、ア.都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の農地、イ.農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域内の農地、ウ.土地改良事業等の施行区域内の農地については、面積に応じ別途算定されます。
【森林】
面積に応じ算定されます。
【その他(雑種地、原野等)】
面積にかかわらず、20万円。
なお、面積による別途算定の方法については、法務省HP(相続土地国庫帰属制度の負担金)をご覧ください。
相続した空き家の処分について
ここまで相続土地国庫帰属制度の概要をみてきましたが、相続した空き家は、建物が存する土地として制度の対象外となってしまうことから、そのままでは国に引き取ってもらうことはできません。
このため、売却や賃貸などによる活用ができないときは、建物を取り壊して更地にしてから相続土地国庫帰属制度を利用することが選択肢となりますが、建物の取り壊しには費用がかかります。
相続した不要な空き家に除却費用を投じるとなると経済的な負担感も増すところですが、空き家が社会問題化するなか、国や都道府県の財源支援も受けて高知県内でも多くの市町村にも、空き家の除却費用の補助制度があります。
国費や県費の配分によって募集件数も毎年増減し、また、市町村によって避難経路沿いに存する空き家に限るなどの条件もありますが、補助金が活用できれば空き家除却の経済的負担を大きく減少することができるため、このような公的支援についても情報収集されてみてはと思います。
当事務所では、相続土地国庫帰属制度、空き家除却補助金、ともに申請サポートを行っていますので、ぜひお気軽にお問合せください。
無料相談のご予約は こちら
この記事の執筆者
.png)
.png)
弊所は、高知県高知市中心部にて相続、遺言、後見といった家族法関係の専門事務所として、主に個人のお客様からのご相談に対応させていただいております。
高齢化の進む日本社会において、特にその進行が顕著な本県にあっては、弊所の提供サービスは社会インフラとしての価値をも有するものとの自負のもと、すべての人が避けて通ることのできない死の前後において、人の尊厳を守り、そのバトンを後世に繋いでいただくための支援に力を尽くしていきたいと考えております。
弊所の「ライフパートナー」という名称には、報酬の対価としての単なるサービスの供給や恩恵的なサービス提供ではなく、敬意をもってサポートを提供することによって、私たちを人生のパートナーとして感じていただければという一方的な願望を込めております。
行政書士ライフパートナーズ法務事務所
代表行政書士 宅地建物取引士 森本 拓也
TAKUYA MORIMOTO
宅地建物取引士登録番号(高知)第005010号
Profile
1993年3月
高知県立追手前高校 卒業
1993年4月
立命館大学産業社会学部 入学
イギリス留学を経て、行政書士資格取得後公務員として約20年勤務した後、行政書士ライフパートナーズ法務事務所開設。
対応地域
高知県中部:
高知市・土佐市・いの町・日高村・須崎市・佐川町・越知町・仁淀川町・土佐町・大川村・本山町・大豊町・香美市・香南市・南国市
高知県西部:
中土佐町・津野町・梼原町・四万十町・黒潮町・四万十市・宿毛市・三原村・土佐清水市・大月町
高知県東部:
芸西村・安芸市・安田町・馬路村・田野町・奈半利町・北川村・室戸市・東洋町
上記地域のほか、全国対応