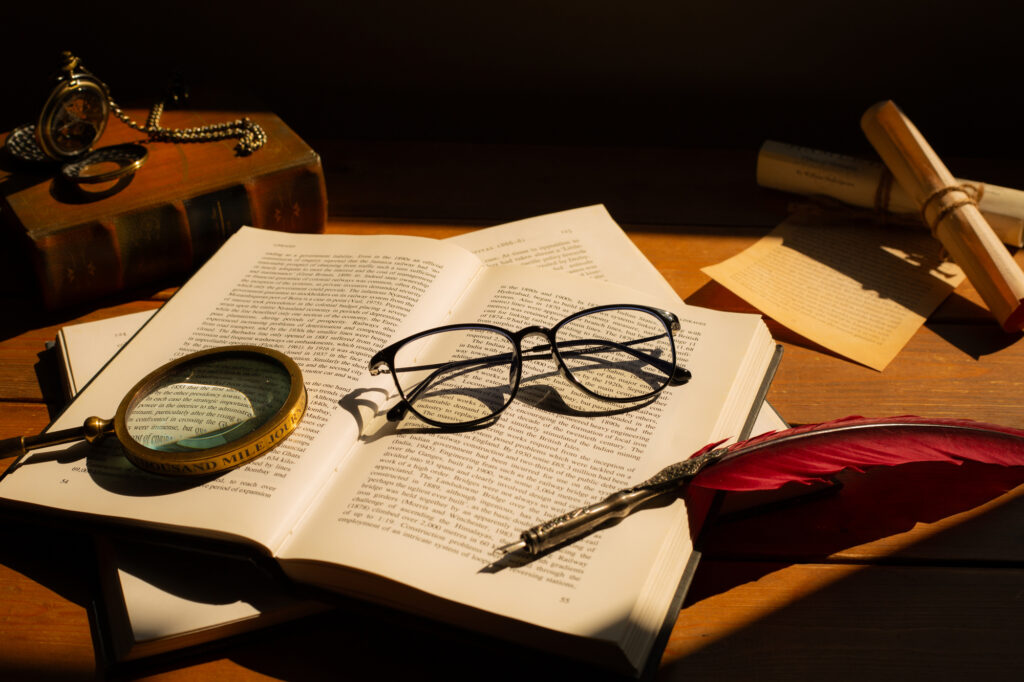
大切な財産を、円満に引き継げるよう、サポートします。
解決できる悩み
- 遺言書をつくりたいが、どのようにしたら良いかわからない。
- 自分の相続で家族が争ってもらいたくない。
- 家族以外に財産を遺したい人がいる。
- 自分で遺言書を書いてみたが、これで大丈夫か不安だ。
遺言を残すことは義務ではありませんし、残さなくても遺産は法律の規定に従って相続人に承継されます。
しかし、法定される相続人以外の人に財産を遺したい場合や、法定される相続分と異なる配分で相続人に遺産を相続させたい場合、希望を実現するためには、遺言を残すことが賢明でしょう。
ご自身で遺言書を作成しようとする場合、相続についての法律の規定がどのようになっているのか、具体的には、相続権が誰にあって、その相続分の割合はいくらか?ということが把握できていれば問題ないようにも思えます。
しかし、以下のような場合はどうでしょうか。
自分名義の家を、一緒に住んでいる配偶者に遺したい場合
法定相続分通りに、配偶者は1/2、子は1/2ずつ、住宅2000万円、預金2000万円なので、配偶者は住宅を、子は預金2000万円とする遺言を残すとしたときに、例えば配偶者に収入が無い場合は、法定相続分通りではいささか不都合です。
このようなケースに対応するため法改正が行われ、現在、遺された同居の配偶者が家賃負担などなく住み続けられる権利として配偶者居住権(遺言、遺産分割協議で定める必要があります。)が定められています。配偶者居住権が500万円、これを除いた住宅の価値が1500万円の場合、配偶者には居住権500万円と預金1500万円、子には住宅所有権1500万円と預金500万円とすることが可能です。子が定期的な収入を得ている場合、遺言によって配偶者居住権を定めることが有効となります。
亡くなった子の嫁・婿など、相続人以外の人に財産を相続させたい。
自分より先に子が死亡しているが、子の配偶者の籍はそのまま残っているので、自分の財産は、民法の代襲相続の規定により子が受けるはずであった遺産を子の配偶者と孫が分け合うため遺言は必要ないであろうとした場合、子の配偶者には遺産は相続されません。
代襲相続の規定では子の配偶者には相続されないため、遺言を残す必要があります。
このように、相続と遺言については、相続人とその相続分がいくらかという法律の規定に加え、遺言の方式や要件その他遺言で定めることができる事項が法定されるほか、財産と相続人をすべて適切に把握する事務負担が伴います。
せっかく残した遺言が、方式に適合しないなどの理由で遺言が無効になったり、財産調査が不十分であったために相続人間に争いを生んでしまったりしないよう、専門家のサポートを検討してみてはいかがでしょうか?
遺言書作成サポート
ライフパートナーズ法務事務所では、依頼者様の状況にあわせて、遺言書の作成をサポートする3つのプランをご用意しています。
フルサポート
遺言書を作成するにあたり、必要となる推定相続人の確認と財産状況の把握を弊所が一括して実施します。
調査によって把握した推定相続人の状況及び財産の状況を、相続法、税法等諸法令の規定に照らし、依頼者様のご意向に沿って、円満な相続を実現するための遺言書の作成を全面的にサポートいたします。
スタンダード
遺言を作成するにあたり、ご自身の財産状況はしっかりと把握している方に対するサポートプランです。
戸籍の収集等の相続人調査は弊所で行いますが、銀行口座通帳のコピー等金融資産に関する資料、不動産に関する資料(直近の固定資産税納税通知書・登記事項全部証明書)、印鑑証明書等は、依頼者様で準備をお願いいたします。
遺言書下書きサポート
ご自身の財産状況や相続人について把握しており、遺言の内容を明確に決めておられる方に対する、遺言書文案の下書きサービスです。
自筆証書遺言として遺言を残される場合に、ご利用を検討ください。
≪ 標準事務と料金 ≫
プラン
下書サポート
推奨
スタンダード
プラン
フルサポート
プラン
こんな方に
おすすめ
自分の財産等が把握できており、遺言を残すにあたって、法的有効性を担保したい方
遺言を残すにあたって、財産状況は把握している方
遺言を残すにあたって、すべてまるごと支援してもらいたい方
料金
22,500
円
54,000
円
76,500
円
ご意向や状況を伺ったうえ、遺言書作成に向けた助言(遺言書の記載方法、遺言の方式、予備的遺言の要否、付言事項など)
印鑑登録証明書の取得
相続人調査
(戸籍取得)
相続関係図作成
不動産調査
(固定資産税名寄帳の取得)
不動産評価
(固定資産税評価額、路線価格の確認)
固定資産税評価証明書取得
(納税通知書を提供いただける場合は省略)
不動産登記事項証明書取得
自動車評価
(その他動産評価は別途)
財産目録作成
遺言書案起案
※公正証書遺言を作成する場合(フルサポート、スタンダード)、上記に加え、公証役場打合せ及び遺言作成当日の同席等のサポートをいたします。
※以下の場合には、追加料金が必要となります。
①戸籍謄本を11通以上取得する必要がある場合:1通につき2,250円
②不動産登記事項証明を11筆以上取得する必要がある場合:1筆につき2,250円
③不動産調査を3市町村以上行う必要がある場合:1市町村につき4,500円
※公正証書遺言を作成する場合、追加料金31,500円と公証役場での手数料が別途必要となります。証人2人(1人あたり9,000円)をお引き受けすることもできます。→公証役場の手数料はこちら(日本公証人連合会HP)
※戸籍調査、不動産調査等における証明書発行手数料などの費用実費は、別途ご負担願います。
※定型・非定型の別については、概ね1回の打合せで条項案を作成できる場合が定型、相続財産に事業資産や国外資産などの資産が含まれる場合、及び相続人の廃除等の特殊な条項を加える場合などは非定型となります。
※相続財産に事業資産が含まれるなど特殊事情のある場合や資産額が5000万円を超える場合、スタンダード108,000円、フルサポート130,500円となります。
【資産額について】
不動産は固定資産税評価額により算出し、負債や遺贈などのマイナスの財産を控除せず算出します。
≪ 各サポートのご依頼の流れ ≫
フルサポート
【ご依頼の流れ】
自筆証書遺言
- お問合せ
- メール又は電話でお問合せのうえ、相談日程を決定。


- 相談・ご契約
- 初回無料相談(約90分)において、ご意向を伺い、遺言・相続についての概要をご説明します。
その際に、お見積とロードマップ(進行表)を提示し、ご依頼いただける場合は契約書を交わしたうえ受任いたします。
依頼をされるかどうかご検討が必要な場合、お返事は後日で結構です。
- 報酬の半額のお支払い
- 契約締結後、報酬の半額のお支払いをお願いいたします。
- 弊所調査等事務
- 推定相続人及び不動産の調査のほか、印鑑証明書・不動産登記事項証明書の取得、不動産・自動車の評価を行います。
依頼者様には、銀行口座通帳のコピー等、金融資産に関する資料のみご用意いただきます。
- 弊所作成事務
- 収集した資料をもとに、相続関係図、財産目録、遺言書原案を弊所にて作成します。
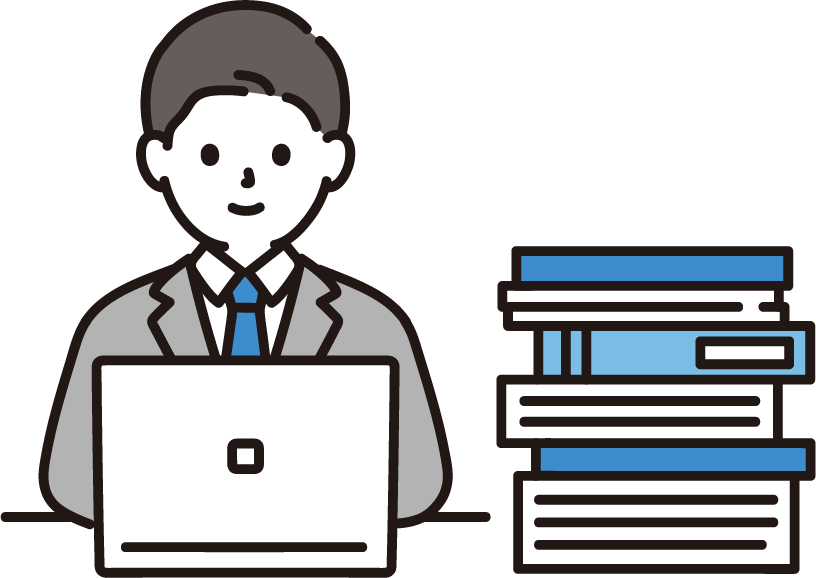
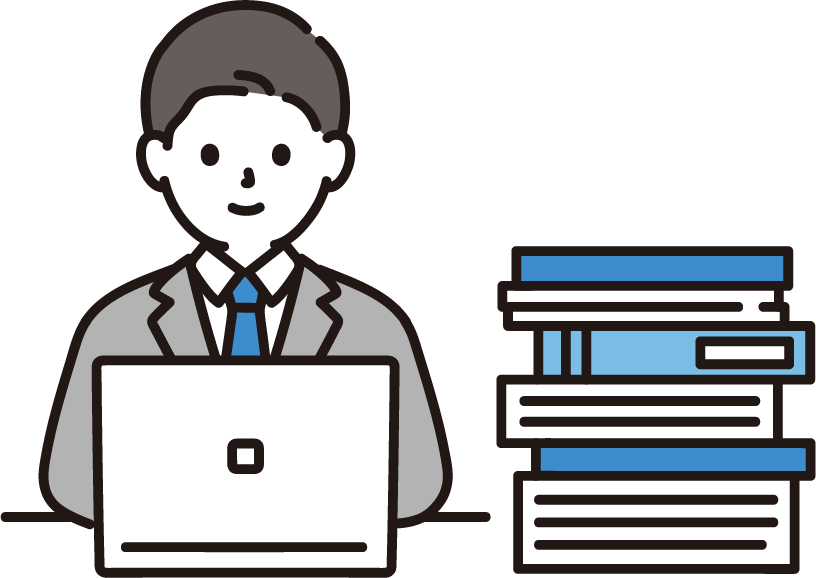
- 打合せ(依頼者様と弊所)
- 弊所にて作成した遺言書原案の内容が、意思を反映しているか依頼者様自身に確認いただきます。


- 遺言書の自書(依頼者様)
- 自筆証書遺言の自書・署名・押印をしていただきます。


- 遺言書の確認(弊所)
- 遺言書の法的要件・契印・封筒の最終確認を弊所が行います。
- 遺言書の封緘(依頼者様・弊所)
- 遺言書に印鑑証明書を添えて封緘します。
この遺言書のほか、遺言書・印鑑証明書の写しその他収集した戸籍謄本等資料を納品し、業務完了となります。
なお、遺言書を遺言書保管所等へ保管されたい場合、別途ご依頼いただけましたらご対応いたします。
- 報酬等残額のお支払い
- 報酬残額と官公署等証明書発行手数料などの費用のお支払いをお願いいたします。


公正証書遺言
- お問合せ
- メール又は電話でお問合せのうえ、相談日程を決定。


- 相談・ご契約
- 初回無料相談(約90分)において、ご意向を伺い、遺言・相続についての概要をご説明します。
その際に、お見積とロードマップ(進行表)を提示し、ご依頼いただける場合は契約書を交わしたうえ受任いたします。
依頼をされるかどうかご検討が必要な場合、お返事は後日で結構です。
- 報酬の半額のお支払い
- 契約締結後、報酬の半額のお支払いをお願いいたします。
- 弊所調査等事務
- 相続人及び不動産の調査のほか、印鑑証明書・不動産登記事項証明書の取得、不動産・自動車の評価を行います。
依頼者様には、銀行口座通帳のコピー等、金融資産に関する資料のみご用意いただきます。
- 弊所作成事務
- 収集した資料をもとに、相続関係図、財産目録、遺言書原案を弊所にて作成します。
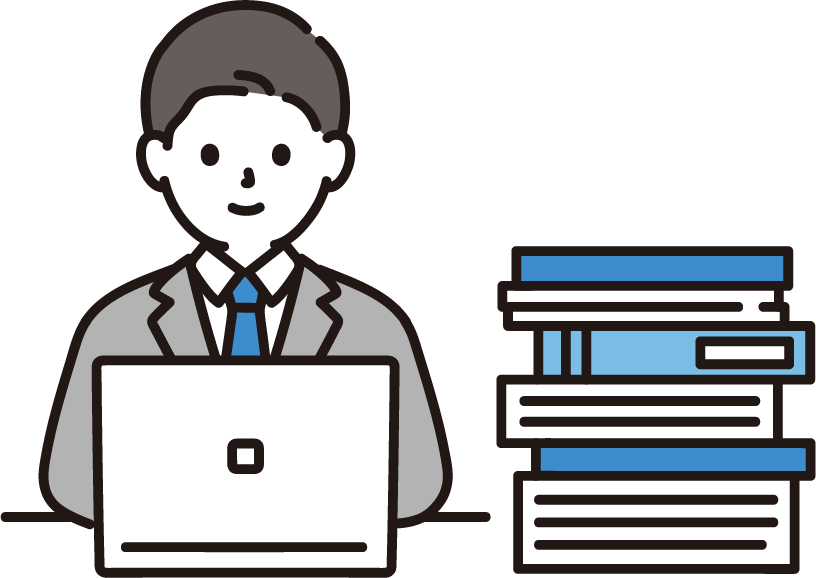
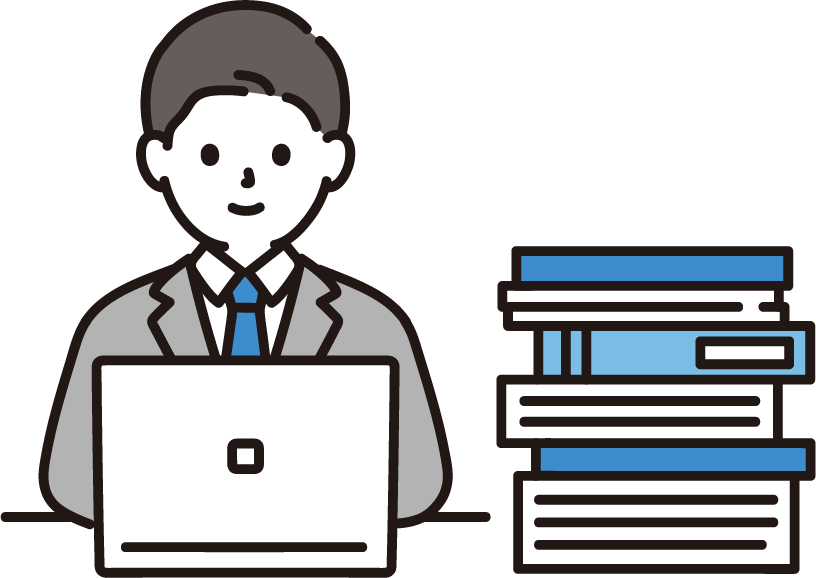
- 打合せ(依頼者様と弊所)
- 弊所にて作成した遺言書原案の内容が、意思を反映しているか依頼者様自身に確認いただきます。


- 打合せ(公証人と弊所)
- 依頼者様に確認いただいた遺言書原案及び収集資料を公証人に報告して文案を検討します。後日、公証人から遺言書文案と公証役場での費用の見積が示されます。
- 打合せ(依頼者様と弊所)
- 公証人から示された遺言書文案を依頼者様自身に確認いただきます。
問題がなければ、公証役場での遺言書作成日程を調整いたします。
- 公正証書遺言作成(依頼者様と証人2人)※弊所同席
- 公証役場において、証人2人の立会いのもと公正証書遺言が作成されます。
公正証書遺言の原本は公証役場に20年保管され、正本と謄本が交付されます。
正本と謄本のほか収集した戸籍謄本等資料を納品し業務完了となります。
- 報酬等残額のお支払い
- 報酬残額と官公署等証明書発行手数料などの費用のお支払いをお願いいたします。


スタンダード
【ご依頼の流れ】
- お問合せ
- メール又は電話でお問合せのうえ、相談日程を決定。


- 相談・ご契約
- 初回無料相談(約90分)において、ご意向を伺い、遺言・相続についての概要をご説明します。
その際に、お見積とロードマップ(進行表)を提示し、ご依頼いただける場合は契約書を交わしたうえ受任いたします。
依頼をされるかどうかご検討が必要な場合、お返事は後日で結構です。


- 報酬の半額のお支払い
- 契約締結後、報酬の半額のお支払いをお願いいたします。
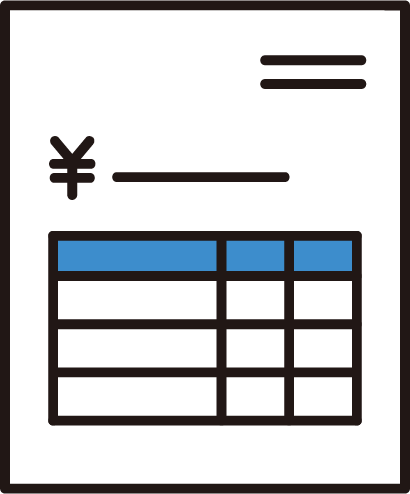
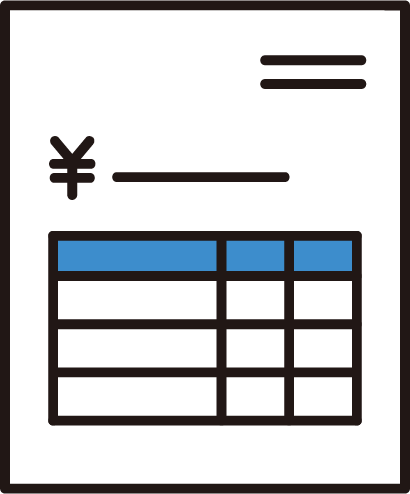
- 弊所調査等事務
- 推定相続人調査のため、弊所にて戸籍収集をいたします。


- 依頼者様資料準備
- 銀行口座通帳のコピー等金融資産に関する資料、不動産に関する資料(直近の固定資産税納税通知書・登記事項全部証明書)、印鑑証明書等をご準備願います。


- 弊所作成事務
- 依頼者様から提供いただいた資料情報と弊所収集資料をもとに、相続関係図、財産目録、遺言書文案を弊所にて作成します。
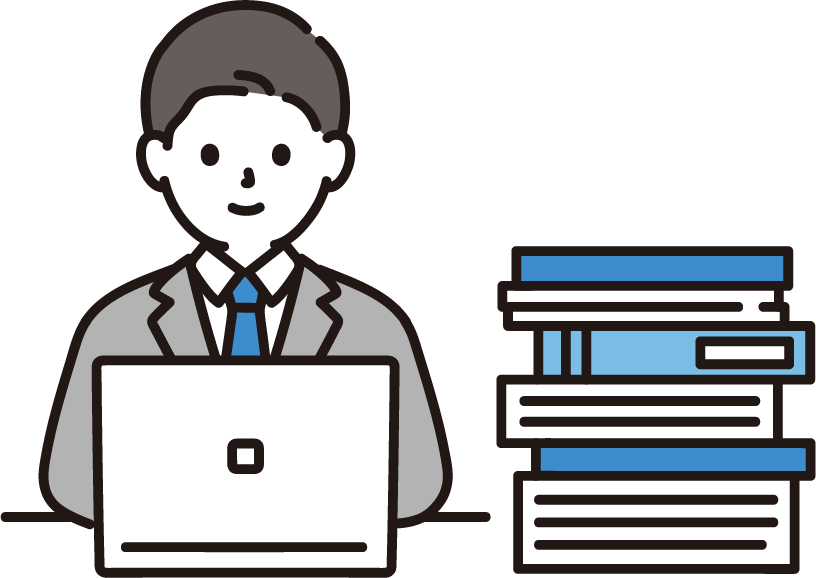
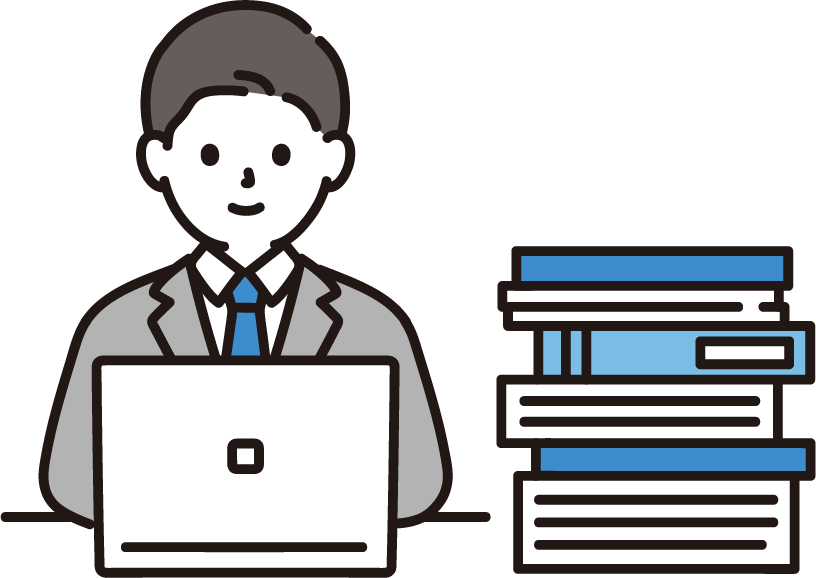
- 打合せ(依頼者様と弊所)
- 弊所にて作成した遺言書文案の内容が、意思を反映しているか依頼者様自身に確認いただきます。
問題がなければ、文案をもとに遺言書の自書を行っていただきます。


- 遺言書の自書(依頼者様)
- 自筆証書遺言の自書・署名・押印をしていただきます。


- 遺言書の確認(弊所)
- 遺言書の法的要件・契印・封筒の最終確認を弊所が行います。
- 遺言書の封緘(依頼者様・弊所)
- 遺言書に印鑑証明書を添えて封緘します。
この遺言書のほか、遺言書・印鑑証明書の写しその他収集した戸籍謄本等資料を納品し、業務完了となります。
なお、遺言書を遺言書保管所等へ保管されたい場合、別途ご依頼いただけましたらご対応いたします。
- 報酬等残額のお支払い
- 報酬残額と官公署等証明書発行手数料などの費用のお支払いをお願いいたします。


※公正証書遺言の流れについては、本ページ上部の「フルサポート」欄の「ご依頼の流れ」をご覧ください。
遺言下書サービス
【ご依頼の流れ】
- ご依頼
- メール又は電話でご依頼ください。弊所より手続きの流れ等をご案内しますので、ご不明な点があれば、その際にお問合せください。


- 遺言下書きサービス依頼書等のご送付
- 依頼者様あてに「遺言下書きサービス依頼書」及び「遺言下書きサービスヒアリングシート」を郵送します。
依頼者様には必要事項を記入いただき、弊所あて郵送してください。
※弊所からの郵送ではなく、下記よりダウンロードのうえご記入いただき、弊所あて郵送していただいても結構です。
※署名・押印が必要な個所の氏名だけは、自書していただくようお願いいたします。
- 弊所作成事務
- 依頼者様から提供いただいた資料により「自筆証書遺言の下書き」及び「財産目録」を作成いたします。
作成完了と料金等支払いのご連絡を差し上げます。
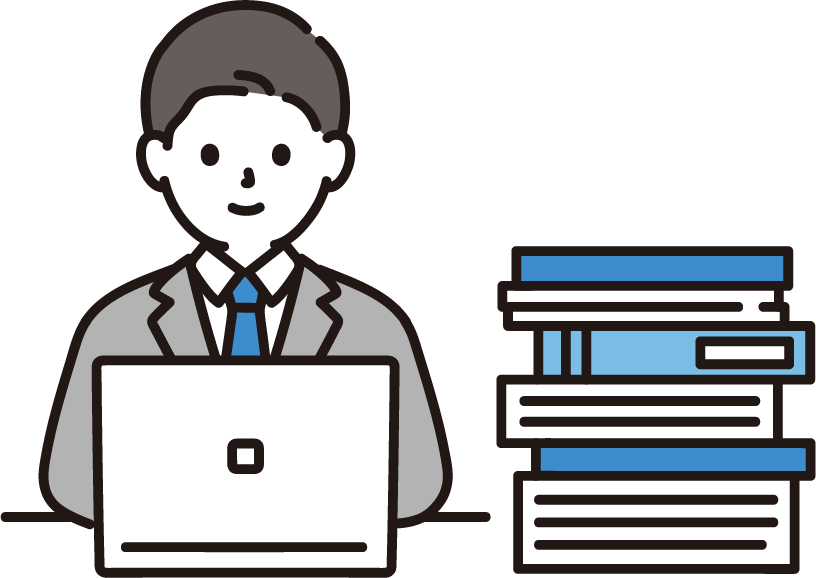
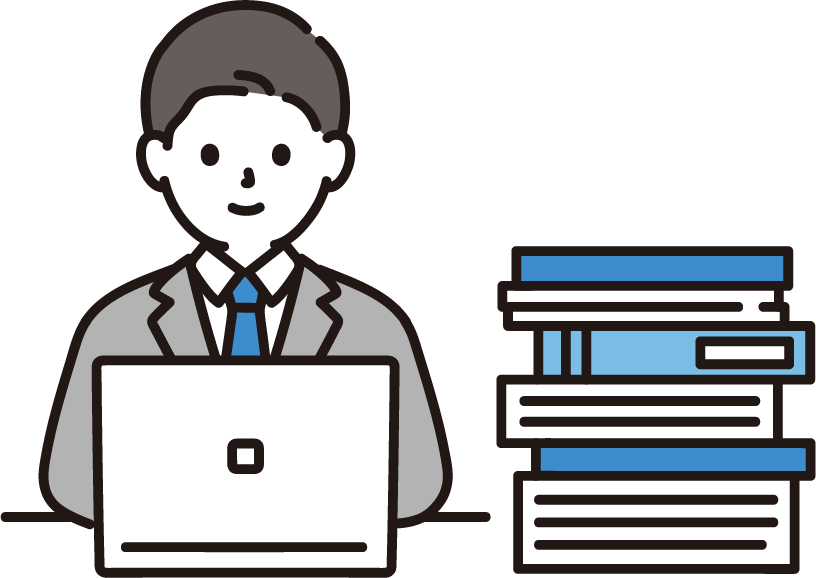
- お支払い
- 料金及び弊所郵送料をお支払いをお願いいたします。


- 「自筆証書遺言の下書き」及び「財産目録」の引き渡し
- 料金等のお支払いの完了を確認後、「自筆証書遺言の下書き」、「財産目録」、「遺言書記載例」、「封筒記載例」、「領収証」、「遺言書作成の手引き」を依頼者様のもとへ送付いたします。
- 下書きの自筆等(依頼者様)
- 遺言書の完成には、依頼者様ご自身の手で全文を自書し、財産目録の全ページに署名押印をする必要があります。
お送りする「遺言書作成の手引き」を参照し、法的に有効な遺言書を完成していただきます。


- アフターフォロー
- 完成した遺言書の法的有効性のチェックも別途賜ります。
料金は、別途7,000円(税込み)+郵送料となりますが、ご検討ください。


無料相談のご予約は、こちら
この記事の執筆者
.png)
.png)
弊所は、高知県高知市中心部にて相続、遺言、後見といった家族法関係の専門事務所として、主に個人のお客様からのご相談に対応させていただいております。
高齢化の進む日本社会において、特にその進行が顕著な本県にあっては、弊所の提供サービスは社会インフラとしての価値をも有するものとの自負のもと、すべての人が避けて通ることのできない死の前後において、人の尊厳を守り、そのバトンを後世に繋いでいただくための支援に力を尽くしていきたいと考えております。
弊所の「ライフパートナー」という名称には、報酬の対価としての単なるサービスの供給や恩恵的なサービス提供ではなく、敬意をもってサポートを提供することによって、私たちを人生のパートナーとして感じていただければという一方的な願望を込めております。
行政書士ライフパートナーズ法務事務所
代表行政書士 宅地建物取引士 森本 拓也
TAKUYA MORIMOTO
宅地建物取引士登録番号(高知)第005010号
Profile
1993年3月
高知県立追手前高校 卒業
1993年4月
立命館大学産業社会学部 入学
イギリス留学を経て、行政書士資格取得後公務員として約20年勤務した後、行政書士ライフパートナーズ法務事務所開設。
