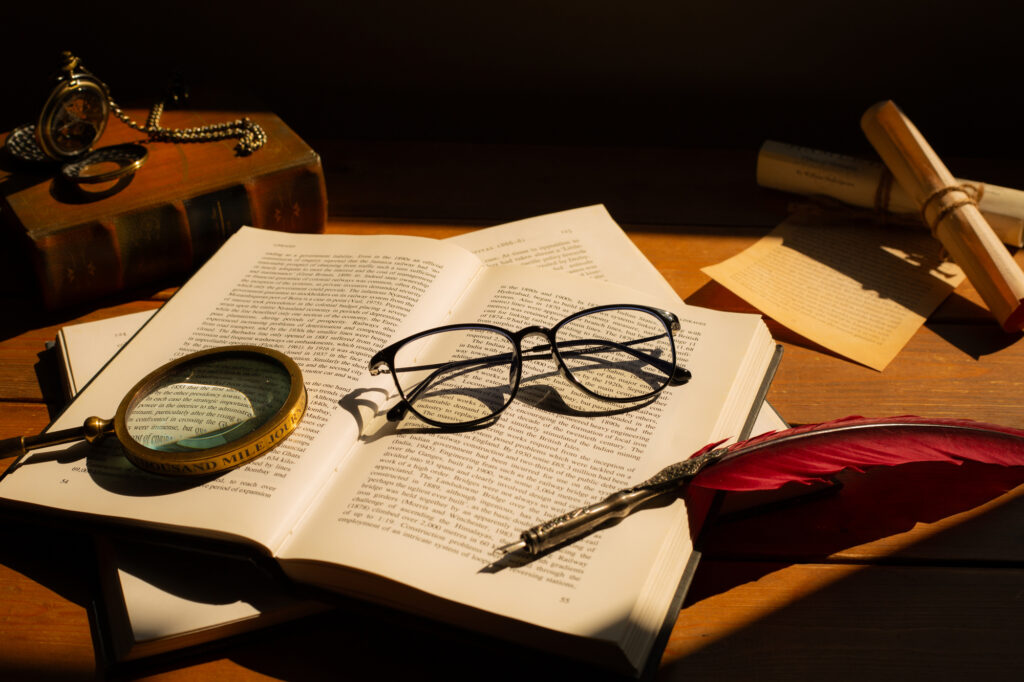
自己決定の尊重と本人保護の要請との調和
昼食にカップラーメンを食べるか、コンビニで総菜パンを買って食べるか、どの総菜パンを選ぶか、自己の不動産を誰に売ろうか、どのような職業に就こうかなど、人生における選択は、それが公序良俗、取締法規、人との約束等に反しない限り、自己の意思により自由に決定し実行できるのが原則です。
例外としては、運転免許や医師免許等一定の危険を伴う行為などは、社会の安全確保のため、法令により一律に禁止したうえ、特定の場合に禁止を解除する(=許可する)とされるものや、義務教育などの義務規定が行政法規にみられるほか、民事法領域にも、公序良俗など社会秩序維持の観点から、一定の限度が設けられたり行為が禁止されたりするものが存在します。
その中でも、本人の行為能力※1に制限を加える成年後見制度等が行為能力制度として民法には規定され、自己決定尊重の理念のもと、取引社会における本人保護と取引の安全が図られています。
※1「行為能力」とは、自らの行為により法律行為の効果を確定的に帰属させる能力をいいます。単独で有効に法律行為を行える能力ともいえます。
行為能力制度とは
民法の定める行為能力制度は、一般的・恒常的に能力不十分とみられる者を一定の形式的基準で画一的に定め、行為時に意思能力があったか否かを問わず、一律に法律行為を取り消すことができるとする制度です。
法律行為の有効・無効は、意思表示のときに表意者が意思能力を有したかどうかによって決されますが、飲酒による明らかな酩酊状態や重度の精神疾患による意思無能力の場合であっても、後日の立証には相応の困難が伴うものです。
行為能力制度の趣旨は、意思無能力であったことの立証の困難性を救済して意思無能力者を保護し、他方、意思能力のない者を定型化することにより相手方の注意を喚起して取引の安全を図る点にあります。
制限能力者として民法は、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人を規定しています。
未成年・成年後見・被保・補助について、各制度の概観
民法における行為能力制度は、未成年に関する基本規定を除き、平成11年の改正により大幅に変更され、自己決定尊重の理念と本人保護の調和の観点から、それまでの禁治産・準禁治産制度にかえて成年後見制度(成年後見・保佐・補助)が設けられました。
これによって、不幸にして十分な精神的能力を備えない人々についての呼称も、旧制度の「行為無能力者」から「制限能力者」となったわけですが、ここでは各制度の内容を概観したいと思います。
(1)未成年者について
保護の対象は未成年者であり、未成年者が親権者又は未成年後見人の同意なくして行った行為は取り消すことができるとして、判断能力の低い未成年が悪賢い他人に食い物にされないようその保護が図られています。
また、親権者等には代理権、同意権、追認権が認められています。
ただし、①単に利益を得、又は義務を免れるべき行為、②親権者などの法定代理人が処分を許した財産を目的とする行為、③法定代理人によって許可された営業に関する行為については、未成年者が単独で行うことができます。負担のない贈与を受ける場合や小遣いでおもちゃを購入する場合などが該当します。
また、子の認知や15歳に達した未成年の遺言なども単独で行うことができる行為です。
(2)成年被後見人について
成年被後見人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者で、家庭裁判所によって後見開始の審判を受けた者をいいます。
家庭裁判所への審判の請求は、本人、配偶者、4親等内の親族、検察官などから行われますが、65歳以上の者については、老人福祉法の規定により市町村長も請求することができます。
後見開始の審判がなされると家庭裁判所に選任された後見人が就任します。
同意を予め与えても、そのとおりの行為をすることが本人には期待できないことから、後見人には同意権がありませんが、代理権、追認権、取消権が認められており、これらをもって本人保護が図られるというのが成年後見制度です。
ただし、成年被後見人も、日常生活に関する行為のほか、婚姻、離婚などの一定の身分法上の行為は単独で有効に行うことが可能です。
平成11年の民法改正においては、高齢化の進展とともに制度需要が高まることから、より使われやすい制度とする点に主眼が置かれ、後見人を1人に限る規定の廃止、夫婦の一方を当然に後見人とする規定の廃止、法人に関する規定の新設、家庭裁判所の成年後見人に対する監督権限の強化、プライバシーに配慮した新たな登記制度の創設などが行われました。
(3)被保佐人について
被保佐人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者で、家庭裁判所によって保佐開始の審判を受けた者をいいます。
保佐制度の目的は、重要な財産の減少・消費の防止であり、被保佐人は、民法第13条に列挙される保佐人の同意が必要な重要な財産上の行為を除いては、日常生活に関する行為、その他財産行為を単独ですることができます。
保佐人には、取消権と追認権が認められますが、代理権については、本人の同意を要件に家庭裁判所が付与した場合のみ特定の法律行為について認められます。
(4)被補助人について
被補助人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者で、家庭裁判所によって補助開始の審判を受けた者をいいます。なお、本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意が必要です。
成年後見人が旧禁治産者に、被保佐人が旧準禁治産者に対応するのに対し、被補助人は平成11年改正により新たに設けられた制度であって、従来の禁治産・準禁治産では保護されなかった者を保護の対象とする制度です。
被補助人は、民法第13条に列挙される行為のうち補助人の同意が必要であるとして家庭裁判所が定めた特定の行為を除いては、単独ですることができます。
補助人には、取消権と追認権が認められますが、代理権については、本人の同意を要件に家庭裁判所が付与した場合のみ特定の法律行為について認められます。
任意後見について
任意後見とは、本人の判断能力が不十分となった場合に備え、療養看護及び財産の管理に関する事務の一部又は全部を任意後見人に委託し、代理権を与える契約を締結し、いざ支援が必要となった段階で支援を受けることを可能とする制度です。任意後見契約に関する法律に定められ、契約は公正証書で締結する必要があります。
任意後見人の選任は、本人の判断能力が十分なうちに、本人の意思で行うことができるため、認知症等を発症してから家庭裁判所により後見人が選任される成年被後見人制度と比較すると、誰に支援してもらうかの選択が確実に行えるのが利点です。
【任意後見と法定後見】
| 任意後見 | 成年後見(法定後見) | |
| 後見人選定の時期 | 本人の判断能力が十分な時期 | 本人の判断能力が不十分となってから |
| 後見人選定の主体 | 本人 | 家庭裁判所 |
| 報酬の決定 | 契約による | 家庭裁判所が決定 |
| 後見人の代理権 | ○ | ○ |
| 本人の行為についての後見人の取消権 | × | ○ |
認知症等を発症し、本人の判断能力が低下した場合、本人・親族等・任意後見受任者(任意後見人となる者)が家庭裁判所に対し任意後見監督人の選任請求を行い、任意後見監督人が就任した時点から任意後見が開始します。
任意後見監督人には、弁護士など法的知見のある専門家等が家庭裁判所により選任されます。任意後見人の事務の執行は任意後見監督人のチェックを受けることとなります。
なお、任意後見契約を結んでも、認知症等を発症しなければ契約が開始されることはありません。
以上、行為能力制度について概観しましたが、法は、自己決定の尊重を原則として、人々の意思能力の様々な程度を予想し、その程度によって本人保護のための制度を準備しているということがお分かりいただけたかと思います。
≪無料相談のご予約はこちら≫
この記事の執筆者
.png)
.png)
弊所は、高知県高知市中心部にて相続、遺言、後見といった家族法関係の専門事務所として、主に個人のお客様からのご相談に対応させていただいております。
高齢化の進む日本社会において、特にその進行が顕著な本県にあっては、弊所の提供サービスは社会インフラとしての価値をも有するものとの自負のもと、すべての人が避けて通ることのできない死の前後において、人の尊厳を守り、そのバトンを後世に繋いでいただくための支援に力を尽くしていきたいと考えております。
弊所の「ライフパートナー」という名称には、報酬の対価としての単なるサービスの供給や恩恵的なサービス提供ではなく、敬意をもってサポートを提供することによって、私たちを人生のパートナーとして感じていただければという一方的な願望を込めております。
行政書士ライフパートナーズ法務事務所
代表行政書士 宅地建物取引士 森本 拓也
TAKUYA MORIMOTO
宅地建物取引士登録番号(高知)第005010号
Profile
1993年3月
高知県立追手前高校 卒業
1993年4月
立命館大学産業社会学部 入学
イギリス留学を経て、行政書士資格取得後公務員として約20年勤務した後、行政書士ライフパートナーズ法務事務所開設。
