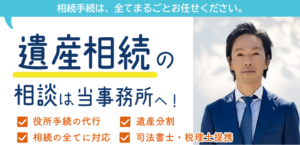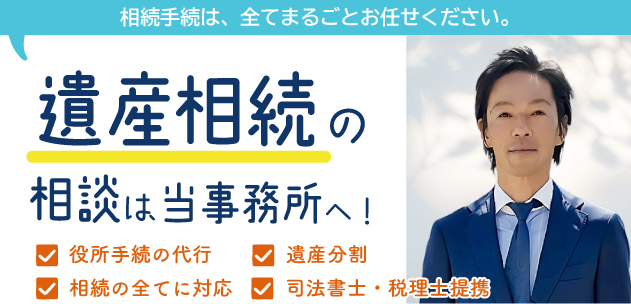
相続においては、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人に引き継がれるのが原則です。
しかし、多額の負債がありマイナスの財産のほうが多い場合などは、相続人が大きな経済的負担を背負い込むこととなります。
このような場合に、プラスの財産の承継を放棄して相続人がその経済的負担を免れることができる制度として、相続放棄があります。
その他、相続人全員によって、マイナスの財産の負担をプラスの財産の範囲に縮減する限定承認も民法は規定していますが、本稿では、相続放棄を選択する場合に注意すべきことを解説します。
なお、相続制度全般については→「相続とは? 相続制度を高知の行政書士が解説。」を、相続の承認・放棄・限定承認については→「相続の承認、相続放棄、限定承認を高知の行政書士が解説。」で詳しく解説していますので、そちらをご覧ください。
相続放棄について
まず、相続放棄とは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月の間に特に意思表示をしなければ被相続人の相続財産を承継し得るという状況を、相続人の意思によって一切承継しないとする意思表示のことをいいます。この意思表示は、家庭裁判所への相続放棄の申述によって為される必要があり、その他の方式で行っても無効とされます。詳細な法的解説は別稿で行っていますが、相続放棄は、被相続人が債務超過である場合に、相続人が不利益を回避するために利用されるのが典型といえます。
相続放棄ができなくなる法定単純承認とは
被相続人が債務超過の場合には、多くの人が相続放棄を検討しますが、相続開始後3か月以内という熟慮期間内に放棄しなければならいという期間制限に加え、相続財産を処分してしまった場合などに相続を単純承認したものとみなされる法定単純承認には注意が必要です。
負債も含めて被相続人の権利義務を無限に承継することとなってしまう事由を、民法は下記のように定めています。
民法(抜粋)
(法定単純承認)
第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
それでは、民法第921条の定める法定単純承認事由について、各号の規定を解説していきたいと思います。
相続財産を処分したとき(1号)
まずは、相続財産を処分した場合です。被相続人名義の住宅を売ってしまった場合などが典型ですが、ここでいう「処分」には、売却などの法律行為のほか、取り壊しなどの事実行為も含まれる点に注意が必要です。
ただし、壊れかけた空き家の修繕などの保存行為、そして民法第602条に規定される短期賃貸借(山林10年、土地5年、建物3年、動産6ヵ月を超えない期間の賃貸借)の場合は、「処分」に該当することなく、単純承認をしたものとみなされることはありません。
また、「処分」は、相続開始の事実を相続人が知ったうえで為される必要があることから(最判昭42.4.2)、知らずに相続財産を売却などしてしまった場合には、単純承認をしたものとみなされることはありませんし、失火による相続財産である建物の滅失など故意でない場合も「処分」には該当しません。
ここまででは、民事法の一般解釈基準である保存行為、管理行為は当然に処分行為ではなく、本条の「処分」にも該当しないと解釈しそうになりますが、法の一般解釈上は管理行為と評価されるであろう賃貸物件の賃借人への賃料の請求が「処分」に該当するという判例(最判昭37.6.21)があることから、本条の「処分」には、短期賃貸借を除き管理行為を含むと解釈すべきでしょう。条文の文言上も、「保存行為と管理行為」とは規定せず、「保存行為と602条の期間を超えない賃貸」と規定していることからもこの解釈基準が妥当するでしょう。
さらに、本号が適用されるのは、相続放棄又は限定承認をするまでの間の「処分」についてであり、相続放棄又は限定承認が有効に行われて以降の相続財産の売却などについては、「私にこれを消費」するなどの状況があってその行為が第3号に該当するとされない限り、本号の「処分」には該当せず、単純承認をしたものとみなされることとはならない(大判昭5.4.26)という点についても留意する必要があります。WEB上では、相続放棄後の相続財産の処分がすべて法定単純承認事由に該当するというような記事が散見されますが、本記事をご覧の相続放棄という大きな判断を検討している皆さんにあっては、簡潔な結論のみを求めることなく、本稿にお付き合いいただければと思います。
最後に本号の「処分」に該当し、単純承認をしたものとみなされることとなる行為を例示します。なお、上述のとおり、行為が相続の開始を知って為されていること、及び相続放棄・限定承認の前であることが前提となります。
【単純承認したものとみなされる場合】
・賃借人への賃料の支払い請求をしたとき
・短期賃貸借期間(山林10年、土地5年、建物3年、動産6ヵ月)を超える期間を定める賃貸をしたとき
・被相続人に帰属していた債権のについて支払いを請求したとき
・建物や土地、その他動産など相続財産の売却したとき
・弁済期が到来していない債務を弁済したとき
上記以外にも、相続財産に関して為されたその行為が、処分行為や短期賃貸借以外の管理行為に該当する場合には法定単純承認事由にあたり相続を承認したものとみなされる可能性があるため、注意が必要です。
また、これら、特に「弁済期の到来していない債務の弁済」の反対解釈として、弁済期の到来した債務の弁済は本号の「処分」には該当しませんが、被相続人が債務超過の場合に、特定の債権者に対してのみ漫然と相続財産から弁済する行為は、相続財産からは各債権者の債権額の按分でしか弁済を受けられない各債権者の均衡を失することがありますので、相続人自身の財産から弁済する場合を除き、相続財産からの弁済はまずは控え、専門家に相談するべきでしょう。
熟慮期間内に限定承認又は放棄をしなかったとき(2号)
原則として、相続人が、熟慮期間といわれる「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に、限定承認又は相続の放棄をしなかったときは、単純承認をしたものとみなされます。
民法(抜粋)
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
第916条 相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
第917条 相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第九百十五条第一項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
なお、熟慮期間の起算点である「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、被相続人の死亡の事実を知ったことに加えて、それによって具体的に自分が相続人となったことを知ったときをいいますが、判例では「相当な理由があれば、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時を起算点とする」(最判昭59.4.27 家族百選76事件)とも示されており、私も実務において、熟慮期間を大きく徒過しているものの相続放棄の申述が家庭裁判所に受理された事例をみてきました。また、利害関係人等の請求によって熟慮期間が伸長される場合もあることから、相続放棄を希望するものの熟慮期間を徒過してしまったというような場合には、専門家にぜひ相談されることをお勧めします。
また、民法第916条に規定されるとおり、相続人が相続の承認・放棄をしないで死亡したときは、その死亡した相続人の相続人(以下、「後相続人」という。)には、第1の相続についても第2の相続における熟慮期間の起算点が適用されます。
例えば、Aが死亡した2か月後にAの相続人Bが死亡した場合、Bの相続人Cは、Bの死亡を知ったときから3か月以内であれば、A及びBの相続について承認・放棄の意思表示をすることができるということとなります。なお、この場合、Cは、Aの相続について放棄し、Bの相続について承認するなどの判断を行うことも可能です。
そして、民法第917条は、相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、熟慮期間は、その法定代理人が相続の開始があったことを知った時から起算すると規定します。なお、被保佐人には本条の適用がないため、熟慮期間は被保佐人が相続の開始があったことを知った時から進行し、その承認又は放棄は被保佐人が保佐人の同意を得てすることとなります。
相続財産を隠匿・消費などしたとき(3号)
1号及び2号は、相続財産の処分及び熟慮期間の経過を相続人による単純承認の黙示の意思表示とみて規定されている一方、3号は、相続人の背信行為に対する制裁として単純承認の効果を負わせるものです。
相続財産の隠匿、私に(ひそかに)消費、悪意の相続財産目録不記載の場合に、単純承認をしたものとみなされますが、その相続人が放棄したことによって相続人となった者が承認した場合は単純承認をしたものとみなされることはありません。
なお、本号にいう相続財産には消極財産(相続債務)も含まれることに注意が必要です。
まとめ
以上、相続を承認したものとみなされ、相続放棄も限定承認もできなくなる法定単純承認事由と評価される行為についてみてきましたが、相続財産を受け取ることを潔しとしないなどの特殊な場合を除いて、相続放棄を検討するということは被相続人が債務超過である場合であろうかと思います。
このような状況においては、被相続人の債権者である相続債権者の支払い請求も厳しく、放棄を検討する相続人にあっては冷静な判断をすることが困難な状況に至ることも予想されます。前述のとおり、法定単純承認事由には該当しないものの、債権者への相続財産からの偏った弁済などを行うことにも注意が必要となるなど、「これは法定単純承認となるが、これは大丈夫」などというように該当行為を列挙できる程度の知識では思わぬ問題を生じてしまうこともあります。
相続の放棄の検討にあたって、法定単純承認事由への該当性に疑問を生じるような行為が必要な場合は、専門家への相談をぜひ検討していただきたいと思います。
≪ 無料相談のご予約は こちら ≫
この記事の執筆者
.png)
.png)
弊所は、高知県高知市中心部にて相続、遺言、後見といった家族法関係の専門事務所として、主に個人のお客様からのご相談に対応させていただいております。
高齢化の進む日本社会において、特にその進行が顕著な本県にあっては、弊所の提供サービスは社会インフラとしての価値をも有するものとの自負のもと、すべての人が避けて通ることのできない死の前後において、人の尊厳を守り、そのバトンを後世に繋いでいただくための支援に力を尽くしていきたいと考えております。
弊所の「ライフパートナー」という名称には、報酬の対価としての単なるサービスの供給や恩恵的なサービス提供ではなく、敬意をもってサポートを提供することによって、私たちを人生のパートナーとして感じていただければという一方的な願望を込めております。
行政書士ライフパートナーズ法務事務所
代表行政書士 宅地建物取引士 森本 拓也
TAKUYA MORIMOTO
宅地建物取引士登録番号(高知)第005010号
Profile
1993年3月
高知県立追手前高校 卒業
1993年4月
立命館大学産業社会学部 入学
イギリス留学を経て、行政書士資格取得後公務員として約20年勤務した後、行政書士ライフパートナーズ法務事務所開設。
対応地域
高知県中部:
高知市・土佐市・いの町・日高村・須崎市・佐川町・越知町・仁淀川町・土佐町・大川村・本山町・大豊町・香美市・香南市・南国市
高知県西部:
中土佐町・津野町・梼原町・四万十町・黒潮町・四万十市・宿毛市・三原村・土佐清水市・大月町
高知県東部:
芸西村・安芸市・安田町・馬路村・田野町・奈半利町・北川村・室戸市・東洋町
上記地域のほか、全国対応