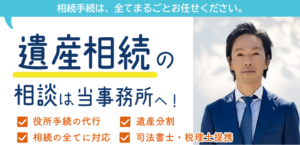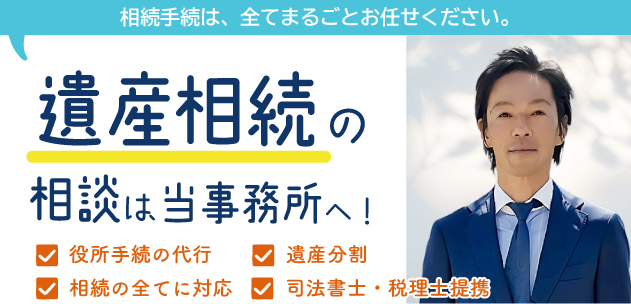
高齢の単身世帯が増加するなか【日本の世帯数の将来推計(都道府県別推計)(令和6(2024)年推計)17頁】、近くに頼れる親族のいない一人暮らしの高齢の方から、「ペットが私の遺産を引き継げる方法を教えてもらいたい。」というご相談をいただくことが多くあります。
残念ながら、ペットに遺産を相続させるということはできませんが、こういったご相談をいただく方の想いは、「私の死後もペットが安心して暮らせるようにしたい。」というものです。
本記事では、飼い主の死後もペットが安心して暮らすために、飼い主が行うことができる「負担付遺贈」について解説します。
猫や犬などのペットに遺産を相続させることはできる?
日本の法律では、ペットは「物」として位置づけられます。よって、ペットは遺産を引き継ぐ主体ではなく、飼い主が何も対策をとらずお亡くなりになると、相続人等に引き継がれる遺産の一部として扱われることとなります。
相続人がいる場合、相続人全員で行う協議によってペットをどなたが引き取るのかを決することとなりますが、相続人のなかに引き取り手がおらず、知り合いの方をあたっても引き取り手が見つからないという状況も飼い主にとっては心配される点です。
また、相続人がいない場合には自分の死後、ペットがどのような生活を送るのかということ点が心配です。
それでは、このような心配を解消し、飼い主の死後もペットが安心して暮らせるために飼い主がとれる生前対策をご紹介します。
ペットが安心して暮らせるよう財産を遺す方法について
上述のとおり、ペットに財産を相続させることは法律上できませんが、多くの方が希望されるであろう、「自分の死後もペットが安心して暮らすために、財産を遺すこと」を実現することは可能です。
法律上一番シンプルなのは、自分の死後にペットをしっかりと飼育してくれる方を探し、その方との間で、委託者の死亡によっても契約が終了することのない、ペットを飼育することを内容とする業務委託契約を締結しておき、委託者の死後、ペットの飼育に対して報酬が支払われるという構成をとることです。
しかし、この方法をとる場合、ペットを飼育してくれた方が報酬の支払いを受けるには、委託者の相続人に請求する必要があり、トラブルの原因ともなりかねないこと、さらに、委託者に相続人がいない場合は、相続財産清算人の選任を家庭裁判所に申立て、相続財産清算人が就任して初めて報酬を受け取れるようになるなどの理由から、実務上はあまり選択することがありません。
また、報酬を契約時に支払うことによりこれらの問題を回避することもできますが、何年も先の業務に対して金銭を支出する必要がでてくることについては、委託者側の心理面や経済面に関して抵抗が大きくもなるため、やはり実務上選択しにくいということとなります。
このような問題の存在から、実務上候補にあがるのが死因贈与、ペット信託、負担付遺贈となりますが、死因贈与やペット信託については、予めペットを引き継いでくれる人と契約を交わす必要があることから、「契約までして引き受けるのは、ちょっと気が重い。」などという心理的ハードルから断られる可能性もでてきます。よって、負担付遺贈を内容とする遺言を残すというのが最も現実的といえるでしょう。
遺産を遺贈する代わりにペットを飼ってもらう「負担付遺贈」
負担付遺贈とは
負担付遺贈とは、遺言に定めることによって行われる贈与すなわち遺贈のうち、遺贈を受ける者(受遺者)に遺贈された財産を受け取る代わりに一定の負担すなわち行為義務を負わせることを定めるものをいいます。
負担の内容としては、残された配偶者の世話をすることやペットの飼育をすることなどを定めることが可能であり、受遺者は、遺贈を受けた財産の価額の範囲内でその負担すなわち行為義務を負います。
民法(抜粋)
(負担付遺贈)
第1002条 負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。
2 受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
なお、負担付遺贈を受けるか否かは、受遺者の自由であり、遺言者の死亡後、特定の財産を遺贈することを内容とする特定遺贈については相続人又は遺言執行者に対する意思表示によって、いつでも遺贈を放棄することができます。下記に示す民法第986条は特定遺贈のみに適用があり、後述する包括遺贈についての放棄は民法第915条以下に従います。
民法(抜粋)
(遺贈の放棄)
第986条 受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
2 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
財産の何分の何という形式で定められる包括遺贈の場合には、受遺者は相続人と同一の権利義務を有するとされることから、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、遺贈の事実を知って3か月以内に放棄の申述をすることによって遺贈を放棄することができます。
ペットを飼ってくれる人に事前にお願いをしておくこと
以上のように、負担付遺贈を含む遺贈一般については、受遺者がこれを拒否することもできるため、ペットを引き取ってもらいたい方に何の相談もせずに遺言書を作成することは得策ではありません。
遺言書を作成する前に、信頼できる方にペットの引取りを打診し、飼育の条件や遺贈する財産の内容など負担付遺贈の内容をしっかりと固めておく必要があります。
遺言者と受遺者すなわちペットを引き取ってくれる人との間で確認しておくべきこととしては、次のような事項があげられるでしょう。
飼い主死亡の連絡
ペットの飼い主が亡くなった場合に、誰がそれを把握し、受遺者に連絡をするのかを決めておきましょう。
ペットの飼育場所
受遺者がペットを引き継いだ後、どこでペットを飼育するのかを決めておきましょう。受遺者の自宅で飼育するというのが受遺者に負担をかけない方法だと思いますが、ペットによってはそれまで生活していた場所と異なる場所で飼育されることによって大きなストレスを抱えることもあります。こういった点も含めて引取り後の飼育場所も話し合っておくと良いでしょう。
情報の伝達
生後91日以上の飼い犬には、①現在居住している市区町村に飼い犬の登録をすること、②飼い犬に年1回の狂犬病予防注射を受けさせること、③犬の鑑札と注射済票を飼い犬に装着することが法律により義務付けられています。登録を証する「鑑札」と「注射済票」は飼い犬に装着しておかなければいけませんが、これらの情報をあらかじめペットを引き継いでくれる人に伝えておきましょう。
また、犬及び猫については、2022年6月1日以降、ペットショップやブリーダーが譲渡する個体にはマイクロチップを付けることが動物愛護法により義務付けられています。引取りの対象の犬又は猫がマイクロチップを付けている場合は、このことについてもあらかじめペットを引き継いでくれる人に伝えておきましょう。なお、マイクロチップには15桁の個体識別番号が記録されています。
その他の条件
上記のほか、ペットの好きな食べ物や病気の罹患歴、かかりつけの動物病院、犬の散歩の頻度など飼育方法について受遺者に履行してほしいことをしっかりと伝えておきましょう。
遺贈する財産
ペット飼い主が死亡した後にペットを引き継いでくれる人にしてもらいたいことをしっかりと伝えたうえ、遺贈する財産についても明確に伝えておきましょう。ここで注意すべきは、飼い主の死後ペットが生きるであろう年数を想定したうえ、その期間に受遺者が行う負担すなわちペットの飼育とその負担費用以上の価値を有する遺贈を準備すべきです。「負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。」という法律の基本的な考えに沿う負担付遺贈を行いましょう。
ここまで、ペットを引き継いでくれる知人などがいることを前提にお話ししましたが、そのような知人がいないという一人暮らしの高齢の方もいらっしゃるかと思います。このような場合には、ペットの保護などに取り組むNPO法人等に相談してみることをお勧めします。
NPO法人等では、保護したペットを、終身の引き取り手である里親さんが現れるまで預かるという保護の仕組みが運用されていることが多いと思いますので、ペットの飼い主が相談に行く段階では里親と直接話をすることはできませんが、里親を選定する際のNPO法人等の基準などを伺い、自分のペットの飼育を任せられるかどうかを判断されてはと思います。
遺言執行者を遺言で指定しておくこと
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理のほか遺言の執行に必要な行為を行う者をいいます。
民法(抜粋)
(遺言執行者の権利義務)
第1012条 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
3 第六百四十四条、第六百四十五条から第六百四十七条まで及び第六百五十条の規定は、遺言執行者について準用する。
頼れる親族が近くにいない方がペットを引き継ぐために負担付遺贈をする場合、遺言者が亡くなったあと遺贈を確実に実行できるよう、信頼できる遺言執行者を定めておくことをお勧めします。
特に、遺言者をする方に相続人がいない方の場合は、ペットを引き取ってくれる受遺者も遺言をした方の財産から現実に遺贈を受けることができないため、必ず遺言執行者を定めるようにしましょう。
なお、遺言執行者を指定する場合も指定せず相続人に遺言の執行を任せる場合も、遺言者の死亡後すぐにペットの引継ぎができるよう準備をしておく必要があります。
具体的には、自宅で生活する遺言者の動きを感知するセンサーを冷蔵庫などに付けておき、24時間動きがなかった場合には、連絡先に通知されるなどの機器・サービスがありますので、このようなサービスを利用し、遺言者に何かあった場合には遺言の執行を任せる者が異変を知り得るという方策を準備しておくことをお勧めします。
負担付遺贈を内容とする遺言書の作成
ここまで見てきたよう、自分の死後にペットを引き継いで飼育してくれる人をみつけ、その人に事前の相談をし、遺言が確実に実現されるための遺言執行者の要否を検討したうえで、負担付遺贈を内容とする遺言書を実際に作成することとなります。
まず、遺言書をどのような方式で作成するかということを検討する必要がありますが、うえの遺言執行者に関する記述のとおり、遺言者が亡くなったときの死亡の把握は別途対策を講じることから、死亡届が提出されて以降の行政間連携により相続人に遺言保管が通知がされる法務局の自筆証書遺言保管制度の指定者通知制度については、遺言の存在が相続人に通知されるからという理由で選択するという実益はここでは存在しません。
よって、遺言書作成の方式については、公証役場での手数料がかかっても公証人が作成することにより法的に確実な内容の遺言が残せる公正証書遺言を作成するのか、費用がかからない自筆証書遺言を作成し法務局の自筆証書遺言保管制度を利用するのかという選択をすることとなりますので、よく検討されると良いと思います。
なお、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の内容については、→別稿「遺言とは? 遺言書作成の前提として押さえるべき知識を行政書士が解説。」をご覧ください。
まとめ
ペットを飼っておられる高齢の方の、自分の身に何かあった際にペットがどうなるかというご心配は大変大きなものだと思います。
本記事では、お亡くなりになった場合の対応策として負担付遺贈による方法の紹介をしましたが、飼い主の長期の入院の際にもペットにとっては同様の問題が起こり得ます。
このような場合には、預け先としてペットホテルなどの民間事業者も候補にあがってくるかと思いますが、飼い主ご自身で連絡や手続きが行える状況にあればまだしも、ここでもやはり誰がペットの一時預かり業者とやりとりするのかといった課題が出てきます。
当事務所では、このような場合にも対応が可能な「見守りサポート」をご準備し、頼れる親族が近くにいない高齢の方々を家族の代わりに支援するサービスを提供しています。また、負担付遺贈を内容とする遺言書作成サポート及び遺言執行者就任もお受けすることができますので、お気軽にご相談いただければと思います。
無料相談のご予約は こちら
この記事の執筆者
.png)
.png)
弊所は、高知県高知市中心部にて相続、遺言、後見といった家族法関係の専門事務所として、主に個人のお客様からのご相談に対応させていただいております。
高齢化の進む日本社会において、特にその進行が顕著な本県にあっては、弊所の提供サービスは社会インフラとしての価値をも有するものとの自負のもと、すべての人が避けて通ることのできない死の前後において、人の尊厳を守り、そのバトンを後世に繋いでいただくための支援に力を尽くしていきたいと考えております。
弊所の「ライフパートナー」という名称には、報酬の対価としての単なるサービスの供給や恩恵的なサービス提供ではなく、敬意をもってサポートを提供することによって、私たちを人生のパートナーとして感じていただければという一方的な願望を込めております。
行政書士ライフパートナーズ法務事務所
代表行政書士 宅地建物取引士 森本 拓也
TAKUYA MORIMOTO
宅地建物取引士登録番号(高知)第005010号
Profile
1993年3月
高知県立追手前高校 卒業
1993年4月
立命館大学産業社会学部 入学
イギリス留学を経て、行政書士資格取得後公務員として約20年勤務した後、行政書士ライフパートナーズ法務事務所開設。
対応地域
高知県中部:
高知市・土佐市・いの町・日高村・須崎市・佐川町・越知町・仁淀川町・土佐町・大川村・本山町・大豊町・香美市・香南市・南国市
高知県西部:
中土佐町・津野町・梼原町・四万十町・黒潮町・四万十市・宿毛市・三原村・土佐清水市・大月町
高知県東部:
芸西村・安芸市・安田町・馬路村・田野町・奈半利町・北川村・室戸市・東洋町
上記地域のほか、全国対応